【初心者向け】療育とは?支援内容・種類・利用方法までわかりやすく解説
「ことばがゆっくり」「お友だちと上手に遊べないかも」育児の中で気になるサインに気づいたとき、「療育」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。このコラムでは、療育についてはじめての方向けに療育の基本や支援内容を、わかりやすくご紹介します。
1. はじめに
「ことばがゆっくり」「お友だちと上手に遊べないかも」育児の中で気になるサインに気づいたとき、「療育」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。このコラムでは、療育についてはじめての方向けに療育の基本や支援内容をわかりやすくご紹介します。

2. 療育とは
療育とは、発達に特性のある子どもが日常生活をよりスムーズに、そして自分らしく生きていくためのサポートです。特定の「正解」に合わせるのではなく、その子の得意・苦手を理解しながら、必要な力を育てていきます。
誰かに合わせるのではなく、その子自身のペースでできる事を増やしていきながら、生活のしやすさや自己肯定感の向上に繋げていきます。
【療育に通っているお子さんの例】
・言葉の発達がゆっくり
・感覚の過敏さや鈍感さがある
・集団行動が苦手
・感情のコントロールが苦手
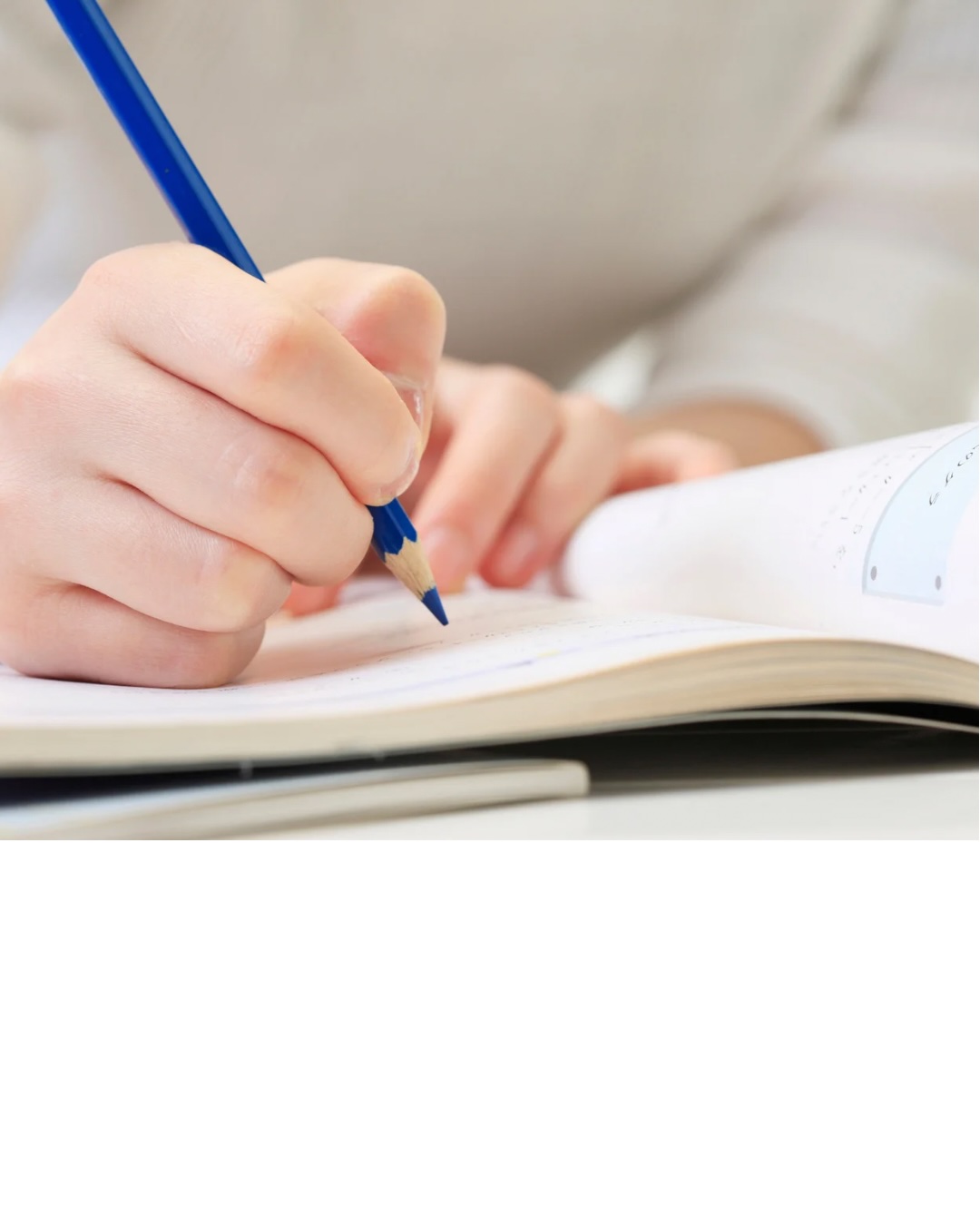
3. 療育の支援内容について
①. SST(ソーシャルスキルトレーニング)
「こんなときどうする?」「困ったときは何て言う?」といった“人との関わり方”を、実際のロールプレイや絵カードを使って学びます。お友だちとのやりとりが苦手な子にとって、とても大切な時間です。
また、実際に起きた出来事や場面を通して行うことや、個別から小集団をテーマに沿って行うことで日常生活への汎化に繋げていきます。
② 机上課題(集中力や手先のトレーニング)
数や文字の認識、手先を使った細かい作業、パズルやカードを使った知的なトレーニングなど、「学ぶ力」や「考える力」を育てることを中心にしています。
学齢期に向けて学習習慣を身につけたり、認知面での発達を促したりすることを目指します。将来の学習意欲や理解力にも繋がりやすいのが特徴です。
③. 感覚遊び・運動あそび
発達に凸凹がある子は、感覚が過敏・鈍麻なことも多いため、感覚統合遊びを取り入れて「からだで感じる力」を整えます。運動が苦手な子にも無理なく取り組めます。
④. 絵カードや視覚支援を使った「見てわかる」支援
言葉だけでは理解が難しい子に向けて、写真やイラストを使って「次に何をするか」が見えるよう工夫があります。安心して行動できる環境づくりを大切にしています。
また、タイプも集団での活動をメインにした「集団療育」とマンツーマンの支援を中心にした「個別療育」があります。お子さまのタイプに合わせて選ぶことが多いです。
療育施設ごとに強みとする支援内容に違いがあるため、その子自身の興味・関心、苦手分野や得意分野、将来的な目標等を意識して見られるといいかと思います。
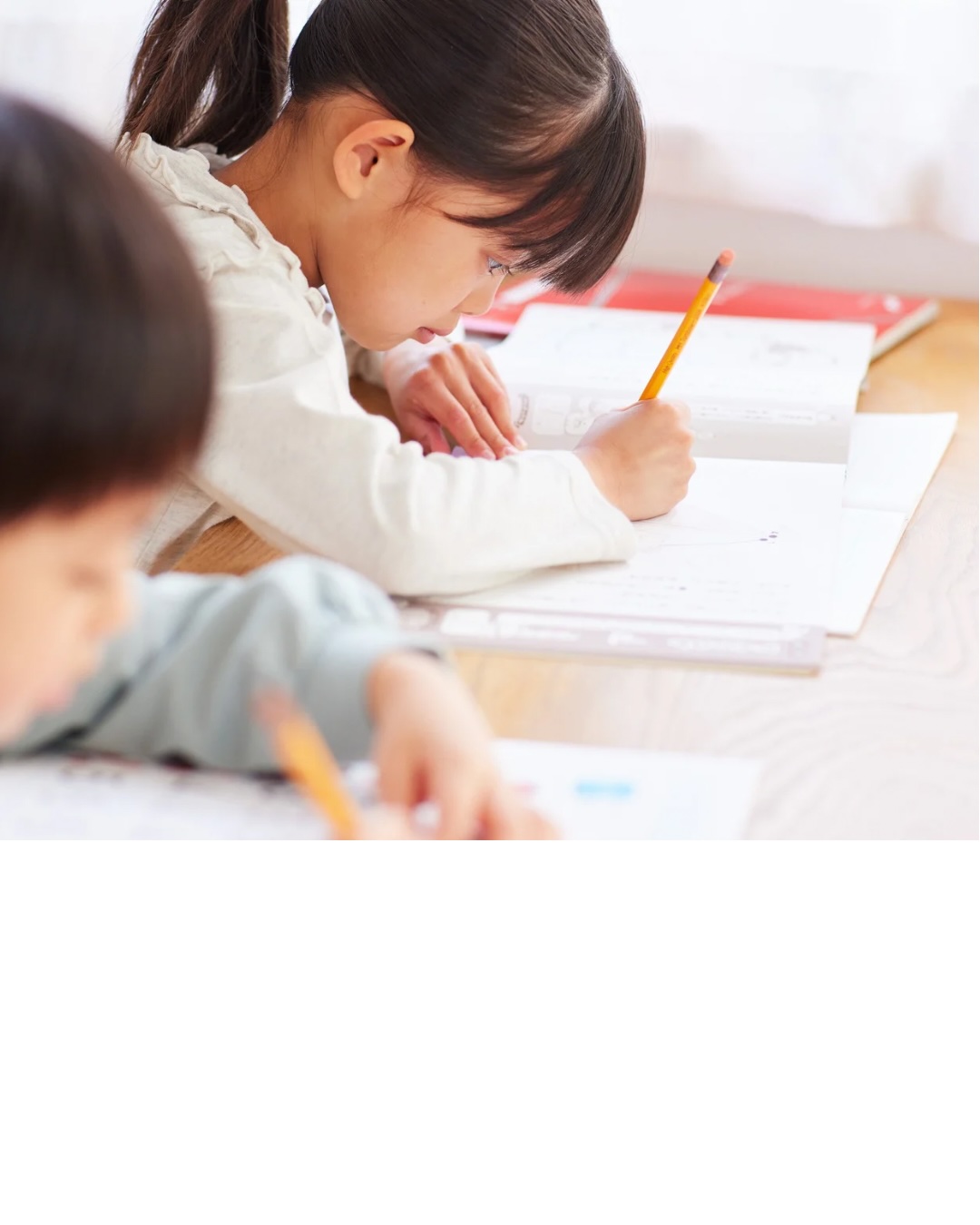
4. 療育を使えるようになるには
療育を利用するためには、「通所受給者証」が必要となります。発達障害の診断がついていない、発達がゆっくりな子やグレーゾーンの子でも、医師に必要と判断されれば取得可能です。
受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。発達が気になる場合は、お近くの自治体窓口、または療育施設でも直接相談を受け付けているところも多いので相談してみてください。

5. まとめ
子どもたち一人ひとりの「できた!」を支えるのが療育です。 大切なのは、「できないこと」に目を向けるのではなく、「できるようになる過程」を一緒に見届けていくこと。もし、発達に不安を感じていたら、まずはお近くの療育施設に相談してみてください。見学や体験から始めることもできます。
発達支援は長期的な取り組みになるため、子どもが楽しく、そして成長を実感できる場所を見つけることが、親子ともに安心して利用できる支援の第一歩となります。
ウォルトのことばアカデミーは、通所受給者証の申請や待機待ちがなく誰でもどこからでもオンラインで始められる新しい選択肢になります。ことばの力を育む一歩を、今すぐ踏み出すことができます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。


